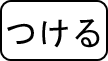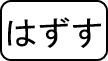ふるさとの歴史
わたしたちのふるさと大沼は、今からおよそ300年ほど前(江戸時代申ごろ)に大沼新田として開かれました。
それまでは、あたり一面萱の原で、オオカミもすんでいました。
また、この地には「宙水」といって降った雨が地中にしみこみにくい場所があり、低いところは水がたまって沼のようになっていました。
大沼神社の南側にも沼(大きな池)があり、大沼とよばれていました。
そのころの大沼地区は淵野辺村の一部でしたが、萱の原を切り開いて畑を作るために、近くの村々(武蔵国の木曾村や根岸村、相模国の鵜野森村や谷口村)から人が集まりました。
はじめは、たったの9件しか家がありませんでしたが、少しずつ人も家も増えていきました。
大沼神社(当時は大沼弁財天〈弁財天は女の神様〉)は、村の鎮守さま(その土地をしずめ守る神様)として、そのころつくられました。
道は、新田通り(大沼通り)と道者みち(大野台小前の道路)があり、武州(今の東京都)方面から大山詣でに行く人たちは、おもに道者みちを使っていました。
村で作られていた主な作物は、麦、アワ、ヒエです。
人々は、朝から晩まで作物作りにはげみましたが、土地がやせていたために収穫量は少なく、生活はあまり楽ではありませんでした。
そこで、クヌギやナラの苗木を植えて雑木林を作り、その木を使って炭焼きを始めました。

埋め立てられる前の大沼(昭和38年)
その炭はなかなか評判がよく、現在の町田市や川崎市あたりまで、荷車にのせて運んでいきました。
また、畑のまわりに桑の木を植えて、養蚕(カイコの飼育)も行われるようになりました。
明治22年(1889年)、淵野辺村はまわりの村(上矢部村、鵜野森村、谷口村、上鶴間村など)と合併して大野村になりました。
大正2年(1913年)には、村ではじめての大野小学校が開校しました。
そして、昭和16年(1941年)には、6つの村と2つの町(大沢村、相原村、田名村、上溝町、麻溝村、新磯村、大野村、座間町〈昭和23年に分離〉)が合併して、日本一大きな「相模原町」になりました。
昭和16年12月に始まった太平洋戦争では、この大沼地区からも多くの若者が出兵し、とうとい命が奪われました。
昭和18年(1943年)、戦争で亡くなった人たちの霊を慰めるために、陸軍の手によって忠霊塔が建てられました。
昭和27年(1952年)からは、慰霊塔として相模原町が管理)塔の中には、戦争で亡くなった人々の遺品や名簿が収められ、慰霊と世界の平和を願って毎年慰霊祭が行われています。
戦後は、日本全体が食糧難になりました。ここ大沼でも食料の増産のために、大沼神社南側に広がっていた沼を水田に作り変えました。「白鷺が舞い降り、稲穂が黄金色に輝く田園の風景がとてもきれいだった」と、神社わきに建てられた石碑に刻まれています。
また、畑の作物の収穫量を増やすために、昭和23年(1948年)から灌漑用水路(畑を潤すための水路)の建設が始まりました。
大沼地区には、木もれびの森から大野台小の裏を通って鵜野森方面へ流れるルートと、緑道途中にあった通称キノコ小屋あたりで分かれ、3丁目公園方向へ流れるルートがありました。
緑道は、使われなくなった潅漑用水路を埋め立ててつくられたものです。

今も残る灌漑用水の面影
昭和29年(1954年)には相模原市となり、昭和40年代に入ると人口が急増してきました。
その結果、畑や水田は宅地に生まれ変わりました。子どもの数も年々増え、昭和44年には大沼小学校、昭和49年には大野台小学校、昭和53年には大野台中央小学校が次々と開校しました。
これまで大沼番地であったこの地域も、人口増にともない、昭和47年に西大沼東大沼、若松と住居表示されるようになりました。
バス路線は、長い間国道16号線(相模原駅~相模大野駅)と北里前通り(相模原駅~上溝~昭和橋~相模大野駅)の2路線しかありませんでした。
特に、大沼通りと北里前通りは砂利道で、雨が降るとぬかるんでたいへんだったようです。
今では、ほとんどの道路が舗装され、昭和58年からは大沼通りにもバス(町田~小田急相模原)が走るようになりました。
また、地域住民の願いであった古淵駅が、昭和63年に開業しました。
完成当時の駅のまわりには、桑畑と昭和石油のグランドくらいしかありませんでしたが、次々と開発が進められ、にぎやかな街並みが誕生しました。

完成直後の古淵駅(裏側から)
更新日:2023年07月13日 13:38:28